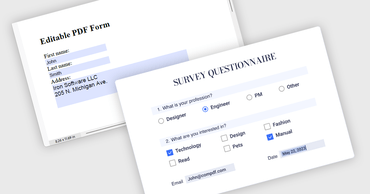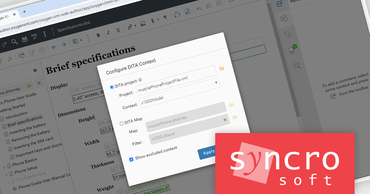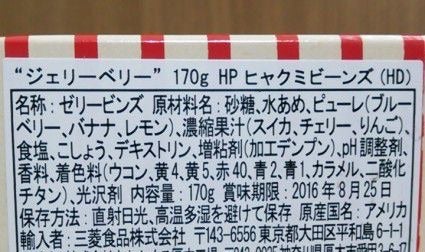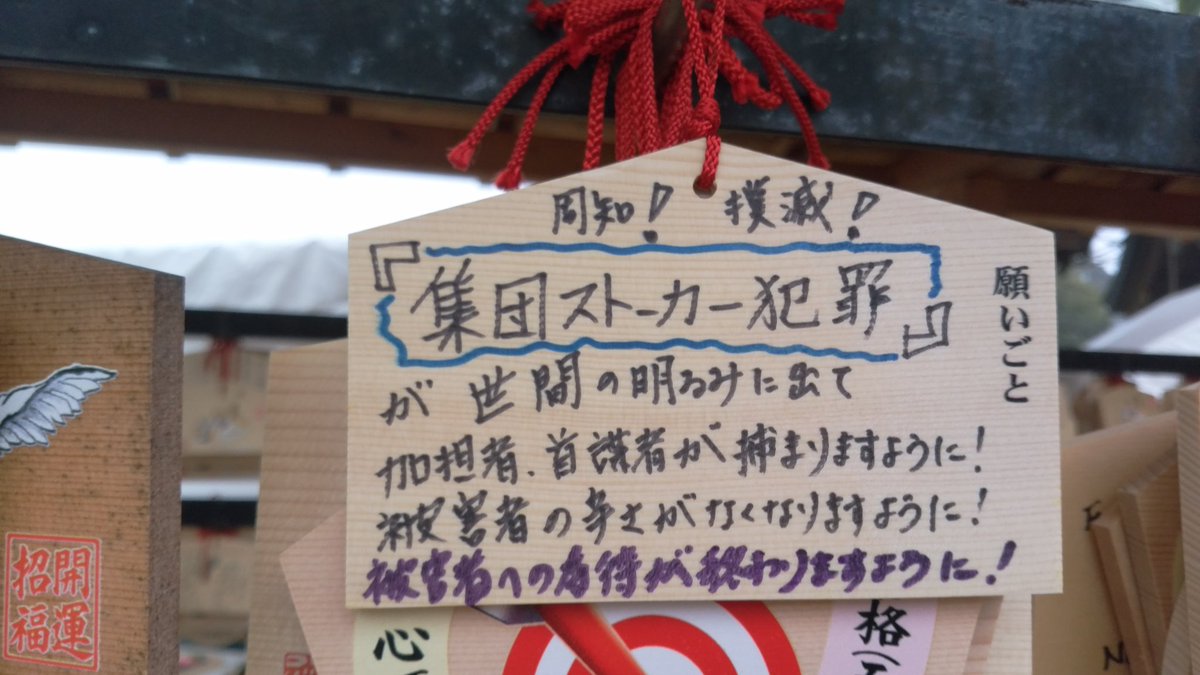「道理で、足が冷えると思ったわ」
私の言葉を聞いて、アザラシは首をかしげていた。アザラシはまだ幼いようだし、ひれも胴体もすべて冷たい氷に触れているのだから、足だけが冷たいという感覚はよくわからないのかもしれない。
とにかく私の家は分厚い氷の家に建っていて、その下はずうっと深く続く水だということをさっき知った。
床の穴からアザラシが出てくるなんてことがなければ、知る由もない話だ。
アザラシは首をかしげていた。
「知らないなんてことがあるものかい? 自分で作っておいて」
「自分で? 私が?」
「そうだよ、泣いて泣いて、その涙で作ったんじゃないか」
「身に覚えがないけれど」
「はーっ、」甲高い声で、小馬鹿にするように、「あきれたね。自分にばれないようにこっそり泣いたんだな、さては」
そう言われても私にはわからない。
自分にばれないように涙を流すなんてことができるだろうか。それも、氷の下にアザラシがすむくらいの量を。
「知らないなんてことがあるものかい? 自分で作っておいて」
「自分で? 私が?」
「そうだよ、泣いて泣いて、その涙で作ったんじゃないか」
「身に覚えがないけれど」
「はーっ、」甲高い声で、小馬鹿にするように、「あきれたね。自分にばれないようにこっそり泣いたんだな、さては」
そう言われても私にはわからない。
自分にばれないように涙を流すなんてことができるだろうか。それも、氷の下にアザラシがすむくらいの量を。
「春が来たらどうなるんだろう」
そんなつもりはなかったのに、不安な声になってしまった。
「春が来て、氷が融けたら……、私の家は」
アザラシは首をかしげる。
「それがわかってるから、春なんて来ないように頑張っていたんじゃないのかい?」
私ははぁっと息を吐いた。そういうふうに言われるような予感はしていたのだ。
「残酷ねぇ、若い子って」
「知らないよ」
「そうよね」
「僕はアザラシだからね」
そうなのだ。アザラシは泳げるのだから。氷が融けて私の家が沈んでしまったって、アザラシにとってはたいした事件ではない。私が一人で困るだけだ。
私がひとりで。
そんなつもりはなかったのに、不安な声になってしまった。
「春が来て、氷が融けたら……、私の家は」
アザラシは首をかしげる。
「それがわかってるから、春なんて来ないように頑張っていたんじゃないのかい?」
私ははぁっと息を吐いた。そういうふうに言われるような予感はしていたのだ。
「残酷ねぇ、若い子って」
「知らないよ」
「そうよね」
「僕はアザラシだからね」
そうなのだ。アザラシは泳げるのだから。氷が融けて私の家が沈んでしまったって、アザラシにとってはたいした事件ではない。私が一人で困るだけだ。
私がひとりで。
「足が冷えると思ってたのよね……」
「そうだね。スリッパ買えば?」
「持ってるの。今もはいてるわ」
「じゃあ、僕は知らないな」
アザラシは首をかしげている。
氷の上でも眠れるのがアザラシなのだから、彼にはあんまりよくわからないのかもしれない。
「そうだね。スリッパ買えば?」
「持ってるの。今もはいてるわ」
「じゃあ、僕は知らないな」
アザラシは首をかしげている。
氷の上でも眠れるのがアザラシなのだから、彼にはあんまりよくわからないのかもしれない。